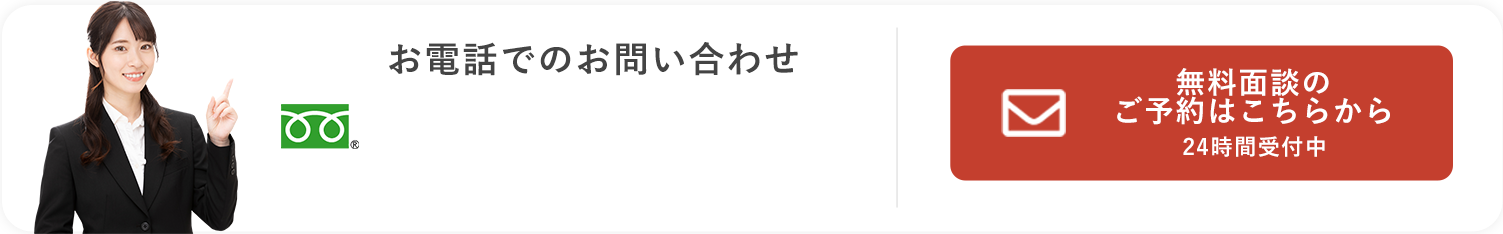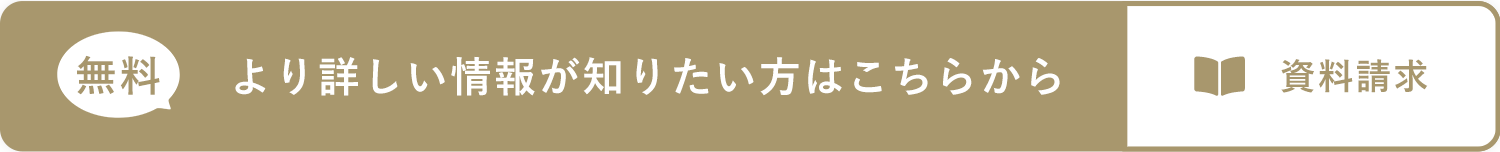こんにちは!多摩・八王子経理代行サービスです。
経理業務のなかでも特に煩雑でミスが起きやすいのが「領収書の管理」ではないでしょうか。「この領収書、何年間保管すればいいの?」「電子化しても大丈夫?」「保存方法を間違えるとどうなるの?」と不安を感じている経理担当者や中小企業の経営者の方も多いと思います。
今回は、領収書の保存期間に関する基本ルールや、電子帳簿保存法への対応ポイント、税務調査時の注意点について詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、
-
-領収書の保存期間と保存方法のルール
-
-青色申告と白色申告による違い
-
-税務調査に備えた実務的な対策
が分かるようになります。
領収書の保管ルールがあいまいなままでは、税務リスクが高まります。
正しい知識を身につけ、スムーズで安心できる経理体制を構築していきましょう。
経理や税務を担当されている方、領収書管理に悩む中小企業の経営者はぜひ最後までお読みください!
領収書の保存期間は何年?基本ルールを解説
領収書の保存期間は、法人と個人事業主で異なるほか、申告区分によっても違いがあります。
法人の場合:原則7年間の保存義務
法人の場合、会社法と法人税法の両方で書類保存が義務付けられています。
領収書などの証憑書類は、法人税法に基づき原則7年間の保存が必要です。
【具体例】
2025年3月決算の法人の場合、2025年5月末に申告 → 2037年5月末まで保存
ただし、税務署から更正の請求ができる期間に関連して、欠損金の繰越控除適用法人などは最長で10年間の保存が求められるケースもあります。
個人事業主の場合:青色申告か白色申告かで違いあり
個人事業主の場合は、以下のように申告形態によって保存期間が異なります。
| 青色申告 | 7年間 |
|---|---|
| 白色申告 | 5年間 |
たとえば、2024年分の申告であれば、青色申告なら2032年3月まで、白色申告なら2030年3月まで保存する必要があります。
領収書の保存形式は「紙だけ」ではない?電子化のルール
電子帳簿保存法で領収書はデジタル化OK
2022年1月より改正された「電子帳簿保存法」によって、領収書や請求書などの証憑書類も電子保存が可能となりました。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
-
改ざん防止の措置
-
-タイムスタンプを付与する
-
-システムによる訂正履歴の管理
-
検索機能の確保
-
-取引年月日・金額・取引先の3項目で検索できること
-
-
すべて電子保存しなくてもOK
領収書の保存には、「紙保存」でも法的に問題ありません。
しかし、電子化することで保管スペース削減や検索性向上といったメリットがあるため、スキャナ保存や会計ソフト連携によるクラウド管理を取り入れる企業が増えています。
領収書保存で注意したい税務調査のチェックポイント
税務調査は「領収書」から始まることが多い
税務調査では、まず領収書や請求書と帳簿の整合性がチェックされます。
特に以下のようなケースは指摘されやすいので注意しましょう。
-
-金額や日付が手書きで修正されている
-
-領収書と帳簿の金額が一致しない
電子保存していても、内容に不備があると無効に
電子保存の際にタイムスタンプの未付与や検索機能の不備があると、
帳簿として認められず青色申告の承認が取り消される可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、信頼性の高い会計ソフトを利用し、運用体制を整えることが重要です。
経理現場でよくある領収書管理の失敗例と対策
ケース1:領収書を封筒にまとめて「どこに何があるか分からない」
対策:月別・取引先別に仕分けし、定期的にチェック
A4用紙に貼り付ける方法や、月ごとのクリアファイルで整理するのが効果的です。
ケース2:電子化したが、システム上の整理ができていない
対策:ファイル名に「日付_取引先_金額」を入れるなどの命名ルールを定める
クラウド会計ソフトであれば、自動で仕訳連動・日付分類されるため、属人化も防げます。
ケース3:電子保存と紙保存が混在し、経理が混乱
対策:一定期間内に一本化し、ルールを社内に周知すること
「電子化するのは○○年度分から」「紙はスキャン後破棄して良い」などの明確なガイドラインを設けましょう。
領収書を正しく保存するためのチェックリスト
領収書の保存に関する混乱を避けるため、以下のチェックリストを運用に活かしてください。
-
□ 青色・白色申告で保存期間を正しく把握しているか?
-
□ 領収書の保存形式(紙/電子)を明確にしているか?
-
□ 電子化の場合、タイムスタンプ・検索機能の要件を満たしているか?
-
□ 月別・取引先別で管理されているか?
-
□ 税務調査が来ても対応できる保管状態か?
このチェックリストを社内で共有すれば、属人化を防ぎ、急な調査対応にも自信を持って臨めるようになります。
まとめ
領収書の保存は「単なる事務作業」ではありません。
正しい保存期間とルールを守ることは、企業の信用力や税務リスク対策に直結します。
電子帳簿保存法の改正により、経理のDX(デジタルトランスフォーメーション)は加速しており、クラウド会計ソフトやスキャナ保存の活用も重要な選択肢となっています。
経理担当者や経営者は、ルールを理解したうえで自社に合った保存方法を選び、業務効率化と法令遵守の両立を目指すことが求められます。
多摩・八王子経理代行サービスでは、電子帳簿保存法対応のアドバイスから、実務的な領収書管理の体制づくりまで幅広くサポートしています。
無料相談も可能ですので、「うちはこの方法で問題ない?」といった素朴な疑問からでも、お気軽にご相談ください。
多摩・八王子経理代行サービスでは、経理代行サービスはもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。貴社に訪問して経理業務を行うので、引き継ぎまで時間がなくても安心です。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込までの各種代行業務や、クラウド会計・クラウド給与・勤怠ソフトの導入もご提案いたします。さらに、クラウドソフト導入にあたり、IT導入補助金の申請サポートも行っており、貴社の業務効率化をお手伝いします。クラウドシステムによって、場所を選ばず給与データの確認や入力が可能となり、リアルタイムでの情報共有も実現します。