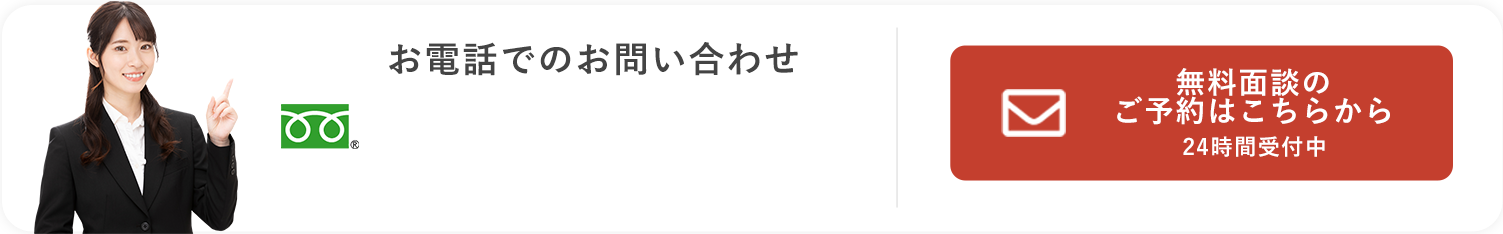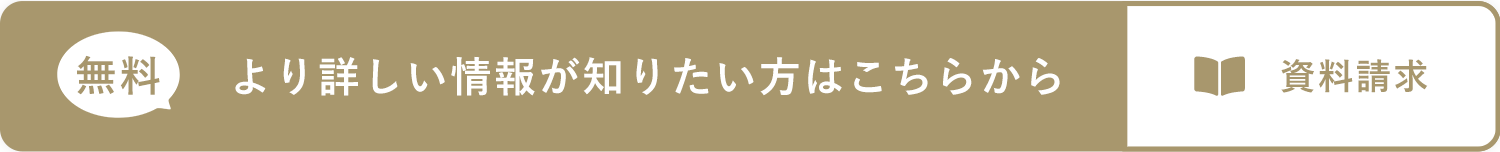企業経営において「役員報酬の決め方」は非常に重要なテーマです。
「いくらにすればいいのか分からない」「税務署から否認されないか不安」「赤字になるかも…」といった悩みを抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、税務リスクを回避しつつ経営の安定を図るための役員報酬の決め方について、税理士としての視点から解説します。損金算入の条件や税務署から指摘されやすいポイント、さらには実務で注意すべきタイミングや具体的なシミュレーション例など、実践的なノウハウを紹介します。
この記事を読むことで、以下のことが分かります:
-
✓役員報酬を「損金」にするための3つの条件
-
①税務リスクが高まるNGな報酬設定とは?
-
②経営状況に合わせた柔軟な報酬戦略の立て方
-
③期末や利益状況に応じた見直しタイミング
これから法人設立する方や、既に会社を経営していて役員報酬の見直しを検討している経営者・経理担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
役員報酬の決め方を間違えると税務リスクが高まる
役員報酬は、経営者の「給料」であると同時に、法人税計算に直結する重要な項目です。適切に設定しなければ、税務上の損金にできない=会社の経費として認められないという問題が発生します。
特に注意すべきは、次の3つの条件です。
税務上、損金にできる役員報酬の3条件
国税庁が定める損金算入可能な役員報酬には、以下のいずれかの形式で支給する必要があります。
-
①定期同額給与:毎月同じ金額で支払われる給与
-
②事前確定届出給与:支給日・金額を事前に税務署へ届け出た賞与
-
③業績連動給与:大企業などで業績に連動して支払われる給与(中小企業では該当しづらい)
これらの条件を満たしていない場合、支払った役員報酬は損金不算入とされ、法人税が増えるリスクがあります。
【実例】役員報酬で税務否認されやすいパターン
税務調査でよく問題になるケースを紹介します。
ケース①:途中で報酬額を変更した
「利益が思ったより出たから、年の途中で報酬を上げよう」といった対応は、定期同額給与の要件違反にあたります。
年の途中で変更すると、変更後の支給分が損金として認められません。
ケース②:賞与を届け出ずに支払った
税務署へ「事前確定届出給与」の申請をせずに役員賞与を支給すると、全額が損金不算入になります。届出の期限(定時株主総会から1カ月以内)を過ぎると無効になるため、注意が必要です。
ケース③:赤字回避のために報酬を大きく減らした
会社の赤字を回避する目的で、期末に役員報酬を減額するケースがありますが、一度定めた金額を安易に変更すると否認リスクが高まります。経営の安定と節税のバランスを取るには、年間計画での見通しが重要です。
経営に役立つ!役員報酬の適正額を決めるコツ
役員報酬の適正額は、税金だけでなく「資金繰り」「社会保険料」「個人所得税」など、複数の要素を見据えて決める必要があります。
ポイント①:法人と個人のトータル税負担を比較する
役員報酬は法人の経費になる一方で、個人の所得税・住民税・社会保険料が発生します。
たとえば、年間報酬を1,200万円とした場合、手取りは約800万円前後になります(扶養の有無や控除によって変動)。
一方、法人に利益を残して法人税を支払うと、資金を会社にプールする選択肢も取れます。
目安として「個人の所得税が33%を超えるなら法人に残した方が有利」と言われています。
ポイント②:利益の見通しと連動させる
創業期や変動の大きい業種では、毎年利益が安定しない場合があります。そのため、役員報酬は、以下のような視点から見直しましょう。
-
✅売上が伸びているか?
-
✅今後の資金調達や投資予定は?
-
✅節税だけに偏らず、経営体力を確保できるか?
経営計画と役員報酬をリンクさせることが、安定経営の第一歩です。
役員報酬の見直しタイミングと手続きの流れ
「いつ見直すべきか」「どうやって変更するのか」も、役員報酬の決定において重要です。
タイミングは「事業年度開始前」が鉄則
役員報酬の変更は、原則として期首(事業年度開始の日)から1カ月以内に定める必要があります。これは、「定期同額給与」の要件を満たすためです。
たとえば、4月決算の会社なら、5月末までに報酬を決定・株主総会で承認する必要があります。
変更には株主総会議事録が必要
役員報酬を決定・変更する場合、次の手続きが求められます。
-
①株主総会での決議
-
②議事録の作成・保管
-
③事前確定届出(必要があれば)
この手続きを怠ると、税務調査で「役員報酬の決定根拠がない」と指摘されるリスクが高くなります。
【税理士の視点】こんな役員報酬戦略がおすすめ
中小企業の経営支援を行ってきた経験から、実際に効果があった役員報酬戦略を紹介します。
ケース①:報酬と配当のバランスを取る
一定の利益が出ている企業では、役員報酬を抑え、配当での利益分配を検討するのも有効です。
配当は法人税後の利益から支払うため損金にはなりませんが、個人での税率が低ければトータルの税負担が軽減されるケースもあります。
ケース②:法人保険を活用して将来に備える
役員報酬を適度に抑え、その分を福利厚生目的の法人保険に振り向けることで、万が一に備えながら税務対策も図れます。
「退職金準備」として、計画的な保険活用も検討の余地があります。
まとめ|役員報酬は税務と経営の両面を見て判断しよう
役員報酬の決め方は、単に「いくらにするか」だけではなく、税務・経営・資金繰り・将来設計と密接に関係しています。
-
✅税務上の損金扱いとなる3要件を理解する
-
✅安易な変更はリスクが高いため事前計画が重要
-
✅法人・個人のトータル税負担を考慮する
-
✅経営状況に合わせて柔軟に戦略を立てる
適切な役員報酬の設定は、企業経営の安定と税務リスク回避に直結します。
専門家のサポートを受けながら、自社にとって最適な報酬戦略を検討していきましょう。
弊社では、中小企業の役員報酬設計をはじめとした税務・会計支援を専門に行っております。
「どの程度の役員報酬が最適か分からない」「税務署に否認されない報酬体系にしたい」などのご相談も、初回は無料で承っております。
お気軽にご連絡ください。